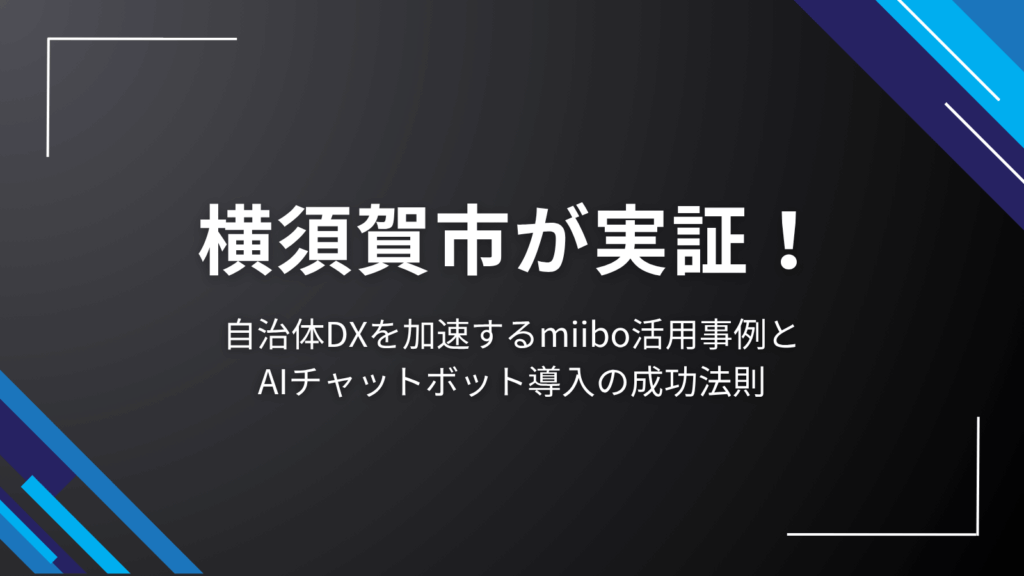
地方自治体のDX推進において、限られた人員と予算で市民サービスを向上させることは喫緊の課題となっています。専門的な技術知識を持つ職員の不足や、セキュアな環境での運用制約、市民への説明責任など、自治体特有の障壁が存在します。本稿では、全国初のChatGPT全庁利用を実現した横須賀市が、miiboを活用してどのように課題を解決し、実用的なAIチャットボットを構築したかを詳しく解説します。
横須賀市は2023年4月から全職員約4,000人がChatGPTを利用できる環境を整備し、年間100万円から200万円という破格のコストで運用を実現しました。さらに、miiboを活用した「他自治体向け問い合わせ対応ボット」では数千件以上の問い合わせに自動対応し、職員の業務負担を大幅に軽減しています。市民向けお悩み相談チャットボット「ニャンぺい」の公開実験では36,042回の問いかけを受け、AIの実用性と課題を明確にしました。これらの取り組みは、非エンジニアの自治体職員がアジャイル開発で実現した点で、他の自治体にとって実践可能な道筋を示しています。
横須賀市のDX推進戦略とAI活用への道のり
横須賀市は2020年4月に「デジタル・ガバメント推進方針」を策定し、「利用者中心の行政サービスの実現」を目指してきました。上地克明市長の「誰も一人にさせないまち」というビジョンのもと、職員がより市民に寄り添いやすい環境を整えることを重視しています。この組織文化が、リスクを恐れず新技術に挑戦する土壌を生み出しました。
デジタル・ガバメント推進室は約30名体制で、情報システムの管理運営と並行して、DX推進の企画実行を担当しています。村田遼馬主任をはじめとする推進担当チームは、BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)やBPM(ビジネスプロセスマネジメント)の手法を数年にわたり実践し、業務の可視化と最適化を進めてきました。この基盤があったからこそ、生成AIという新技術を効果的に活用できたのです。
2023年3月、ChatGPTの可能性に着目した現場職員と、生成AI活用を指示した市長のビジョンが合致し、わずか1か月で全庁利用を開始しました。UI/UXデザイナーの深津貴之氏を生成AI戦略アドバイザーに迎え、「知識を得るのではなく、知識を与えて仕事をさせる」という明確な方針のもと、実用的な活用を推進しています。
miiboが解決した自治体特有の技術的課題
自治体におけるAI活用の最大の制約は、総合行政ネットワーク(LGWAN)の存在です。セキュアな環境で運用される行政データは、インターネット上のAIサービスから分断されており、そのままではAIに読み込ませることができません。横須賀市はこの課題に対し、kintoneを活用した独自の解決策を編み出しました。
まず、LGWAN内の様々な形式のデータをkintoneに集約し、標準化します。次に、このデータをCSV形式で出力し、AIが理解しやすい形に変換します。この工程により、セキュリティを保ちながらAIへのデータ提供を実現しました。村田主任は「機械可読性の高いデータを作成することは、AIを効果的に活用するために非常に重要」と強調しています。
miiboを選定した理由は、RAG(検索拡張生成)環境を簡単に構築でき、Web上で登録すればすぐに使える点にありました。当時、RAGを簡単に構築できるサービスは少なく、技術に明るくない職員でも使いやすいUIであることも決め手となりました。年間のランニングコストも抑えられ、限られた予算内で実用的なシステムを構築できたのです。
実践的なAIチャットボット開発手法
横須賀市は「他自治体向け問い合わせ対応ボット」の開発において、アジャイル開発の手法を採用しました。最初はシンプルなFAQ形式のテキストデータから始め、質問に対して望む回答が得られない場合は、わかりやすい形に整えたり、複数の表現で言い換えたりする工夫を重ねました。現在はGPT-4oを使用することで、こうした工夫なしでも高精度な回答を得られるようになっています。
「ニャンぺい」の開発では、市民向けサービスとして慎重なアプローチを取りました。AIのハルシネーション(誤った情報の生成)リスクを考慮し、あえて「未完成のチャットボット」として公開実験を実施しました。利用者には事前に誤りが生じるリスクを開示し、不具合を「見つけてほしい」という形で協力を求めたのです。
テスト工程では、Python×GPT-4oを活用した自動化システムを構築しました。300件のテストシナリオを30分で処理し、GPT-4oが回答を5段階で自動評価する仕組みにより、効率的な品質管理を実現しています。非エンジニアである村田主任が、ChatGPTの支援を受けながらこのシステムを内製した点は、AIによる能力拡張の好例といえるでしょう。
導入効果と波及効果の実績
「他自治体向け問い合わせ対応ボット」の導入により、ChatGPT全庁利用に関する100社以上の報道機関からの問い合わせ対応が大幅に効率化されました。数千件以上の問い合わせがボットに寄せられ、基本的な質問への対応が自動化されたことで、職員は本来の業務に集中できるようになりました。村田主任は「ボットがなければその都度説明が必要だったことを考えると、時間の短縮が図られている」と効果を実感しています。
「ニャンぺい」の公開実験では、約1か月で36,042回の問いかけがあり、41件の不具合報告を受けました。事前の職員向け検証(4,608回の問いかけで101件の通報)と比較すると、通報率が大幅に改善していることがわかります。これは、プロンプトの改良が功を奏した結果です。
横須賀市の取り組みは、全国の自治体に大きな影響を与えています。「自治体AI活用マガジン」には22自治体1団体が参加し、知見を共有しています。「横須賀生成AI合宿」には定員60名に対し多数の応募があり、抽選を行うほどの人気となりました。市長の「AIの活用をどんどん進めて知見を外に出し、日本全体を良くしよう」という方針のもと、積極的な情報共有が行われています。
今後の展望と他自治体への示唆
横須賀市は、データの標準化がAI活用の鍵であることを実証しました。村田主任は「各種お知らせをパーソナライズする」アイデアを例に、市民一人ひとりに最適な形で情報を届ける未来を描いています。紙の郵送物をラジオ音声やSNSのショート動画に変換するなど、AIの変換技術を駆使した新しい行政サービスの可能性を探っています。
生成AIの技術進化に対しては、特定のサービスに固定せず、柔軟に乗り換え可能な状態を維持することが重要だと村田主任は指摘します。「使用する生成AIをどれか一つに決めて全力投資するのは、現段階ではそぐわない」として、様々なサービスを試しながら最適解を見つけていく姿勢を示しています。
他の自治体がAI活用を進める際のアドバイスとして、村田主任は「生成AIの活用は、ちゃんと役に立つのか、業務をいいものにするのかを考えるのが大前提」としながらも、「技術がすごいスピードで進化する時期はそうないので、進歩の速さも楽しく受け止めて、上手く波に乗れるよう一緒に頑張っていきましょう」とメッセージを送っています。
よくあるご質問
Q
miiboの導入にはどれくらいのコストがかかりますか?
横須賀市の事例では、ChatGPT全庁利用を含めて年間100万円から200万円程度で運用しています。miiboは導入コストが低く、Web上で登録すればすぐに使える点が特徴です。ただし、実際のコストは利用規模や機能要件により変動します。
Q
技術的な専門知識がなくても導入できますか?
はい、可能です。横須賀市の村田主任も非エンジニアですが、miiboの使いやすいUIとChatGPTの支援により、AIチャットボットの構築に成功しました。重要なのは、業務の可視化と標準化を進めることです。
Q
LGWANとの連携はどのように実現していますか?
横須賀市では、kintoneを中継点として活用しています。LGWAN内のデータをkintoneに集約・標準化し、CSV形式で出力することで、セキュリティを保ちながらAIへのデータ提供を実現しています。
Q
「ニャンぺい」の精度はどの程度ですか?
公開実験では36,042回の問いかけに対して41件の不具合報告がありました。固有名詞の間違いや事実と異なる回答などの課題はありますが、プロンプトの改良により精度は向上しています。100%の正確性は困難ですが、実用レベルに達しています。
Q
他の自治体でも同様の取り組みは可能ですか?
はい、可能です。横須賀市は「自治体AI活用マガジン」や「横須賀生成AI合宿」を通じて、積極的に知見を共有しています。重要なのは、完璧を求めすぎず、小さく始めて改善を重ねるアジャイル的なアプローチです。
Q
セキュリティ面での懸念はありませんか?
横須賀市では、個人情報を含まない業務での活用から始め、段階的に適用範囲を広げています。LGWANとインターネットの分離を維持しながら、安全にAIを活用する仕組みを構築しています。
Q
導入から運用開始までどれくらいの期間が必要ですか?
横須賀市では、ChatGPT全庁利用をわずか1か月で開始しました。miiboを使った「他自治体向け問い合わせ対応ボット」も、2023年4月から検証を重ね、同年8月に本格運用を開始しています。小規模な実証実験なら数週間で開始可能です。
横須賀市が示す自治体DXの新たな展開
横須賀市の取り組みは、日本の自治体DXにおける重要な転換点を示しています。全国初のChatGPT全庁利用から始まり、miiboを活用した実用的なAIチャットボットの構築まで、わずか1年余りで実現した成果は、他の自治体にとって大きな希望となっています。特筆すべきは、これらの取り組みが非エンジニアの職員によって推進されたことです。技術的な専門知識がなくても、明確なビジョンと実践的なアプローチがあれば、自治体でもAI活用が可能であることを証明しました。
「生成AI開国の地」と呼ばれる横須賀市は、失敗を恐れず新しい技術に挑戦する文化を醸成しました。「ニャンぺい」の公開実験に見られるように、完璧を求めるのではなく、市民と共に成長していく姿勢は、これからの行政サービスのあり方を示唆しています。横須賀市の事例は、限られたリソースで市民サービスの向上を目指す全国の自治体にとって、実践可能なロードマップとなることでしょう。日本の自治体DXは、横須賀市の挑戦から新たな段階へと進化を続けています。